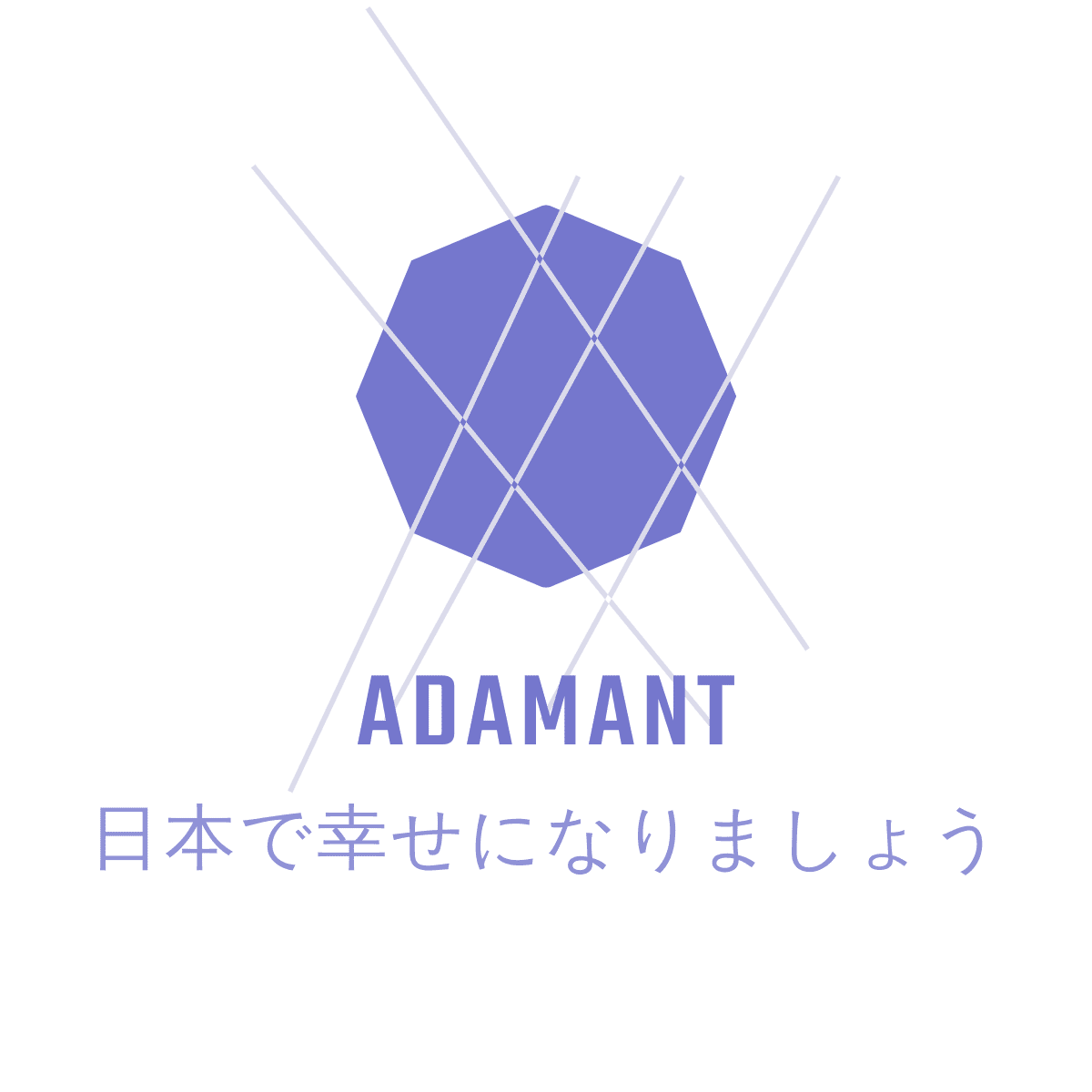ワセダロータリーの入会スピーチ①
今年1月に入会したワセダRCで自己紹介スピーチをしました
▽事務所名の意味はダイヤモンド
当事務所の名前は、アダマント行政書士事務所と言うのですが、アダマントは英語で揺るぎない、不屈の、ダイヤモンドのようなという意味です。アダマースは、ギリシャ語でダイヤモンドという意味でロシアのモスクワの宝石屋さんによくある名前です。結構ロシア的な名前だと思います。
モスクワもペテルブルクもそうですが、ロシアには宝石屋さんがとてもたくさんあります。なぜかというと、ソビエトが崩壊したときにルーブルが紙切れになってしまったからです。それゆえに、ロシア人の皆さんは、金や宝石で財産を持つことに対して非常に積極的で、宝石や貴金属への知識がとても豊富です。それはヨーロッパ人一般もそうかもしれませんが、とにかくその宝石や金を持っておいて、有事のときはそれを身に着けて身一つで逃げ出せるようにしているわけです。
そういうわけで、モスクワやペテルブルクには宝石店など貴金属のお店がとてもたくさんあって、そういうお店に「アダマース」、ダイヤモンドという名前がついていて、それを想起しながら英語のアダマントという名前をつけました。お客様のために揺るぎない不屈の精神、折れない心で頑張るという気持ちを込めています。
ウクライナとロシアは、もともと兄弟関係にある国で、別の国であるとは言い難いような面があります。ウクライナのキエフ公国とモスクワ公国は昔から兄弟関係で、ウクライナがお兄さんで、ロシアは弟なのです。その兄弟同士で今は殺し合っているような状態で私は大変心を痛めています。文化的には、宗教は両国ともにオーソドックスで同じです。同じ宗教の人同士で殺し合っているので、私は、これはかなり問題があると思っています。

▽ロシアに精通していた父、熱血教師の母
母は、中学校で国語の教師をしていました。もう退職していますが、いまだに教え子から連絡が来るぐらい非常に教え子に好かれていた人で、本当に熱血教師でした。金八先生みたいだとよく言われていました。
父は、昨年1月に急逝しました。父は、この感じからしてサラリーマンではないということは分かると思います。映像プロダクションをしていて四谷に会社を構えていました。父は、もともとテレビ局勤務で、ペレストロイカ時代のモスクワにテレビ局駐在員として駐在していました。テレビ局を退職した後も旧ソ連関係のテレビ番組の制作をメインにしていました。ウズベキスタン、タジク、カザフスタン、モンゴルなどに年の半分以上は行っていました。ほかのディレクターは入れないような旧ソ連圏にも取材をさせてもらって、いろいろな番組を作っていました。父が撮ったチェルノブイリ原発事故の後遺症に苦しむ子供たちを取材したNHKスペシャルが、カンヌ映画祭のドキュメンタリー部門で出品されたこともあります。
父は、ロシア語ができた人なので、ロシア語の本が実家の書斎にたくさんありました。キリル文字は、アルファベットとは違うので、不思議な文字だなと思って興味を持っていました。私は、早稲田大学の第一文学部の露文学科卒です。最初は文学部という枠で入るので、特にロシア文学専攻というわけではありませんでしたが、第2外国語でロシア語を取ったことは父の影響があります。父は亡くなりましたが、書斎にある蔵書は全部読めます。それを難なく読めるようになったことに父との絆を感じます。今でも暇なときには、ソビエト時代の映画をYouTubeで見たりして、父が大切にしたロシア文化への理解を忘れないようにしようと思っています。父は、私が子供のときからあまり家にいない人だったので、今も遠いどこかで取材旅行でもしているのかなと思っています。
▽ロシア文学「巨匠とマルガリータ」
早稲田大学に入ったのは両親の影響ですが、もともと本が好きで文学を勉強したいという気持ちがありました。早稲田大学の中央図書館は、日本でも有数の蔵書数を誇る図書館です。しかも、世界各国の図書館から全部取り寄せてもらえます。ですので、文学の研究をするにはとてもいい大学なのではないかと思い、選びました。
もともと私は、行政書士になりたいと思っていたわけではなく、文学の研究者になりたいと思っていました。専門はロシアの20世紀文学を専攻していて、卒論で取り扱ったのはブルガーコフの「巨匠とマルガリータ」という小説です。特に幸運だったのは、もう亡くなられましたが、日本でも一番と言えるぐらいの文学者の水野忠夫先生という方の最後の弟子になれたことです。卒論指導のときに、水野先生に直々にブルガーコフについていろいろ指導をしてもらったおかげで研究がはかどり、ぜひ大学院に行きなさいと言われたので大学院に行きました。
「巨匠とマルガリータ」という作品は、イエスの処刑をしてしまったポンティオ・ピラトの古代イエルサレムの時代を書いた部分と、現代のモスクワの部分が交互に出てくる少し変わった小説です。本当に面白い小説です。どんどん同時並行で関連がない物語が進んでいくのですが、最後でモスクワと古代イエルサレムの描写がピタッと合わさる部分は、叙述のダイナミズムと言われているとても感動する部分です。
この作品は、1929年~1940年にかけて執筆されました。スターリン時代の抑圧された社会の中で、小説家である主人公の「巨匠」が言論弾圧を受けておかしくなってしまうのですが、言論弾圧の中でどのように文学者が生き延びていったのかということが小説の中から読み取れる、20世紀を代表するすばらしい小説だと思います。
作中にヴォランドという悪魔が出てきます。巨匠は、「僕は全てを失ってしまった、全部自分の原稿も焼いてしまった」と言ったときに、ヴォランドが「Рукописи не горят!(ルーコピシィ・二・ゴリャト)」、「原稿は燃えません」と言ってマントからパッと原稿を取り出します。それは、スターリンの圧政に対する文学の勝利を宣言する言葉です。そもそもソ連時代は、言論の自由がありませんでした。作家たちは、地下出版などを出して「Рукописи не горят!」をテーマにして何とか生き延びていた状況でした。水野先生にそういうことをいろいろ教えてもらいました。水野先生は一生の師匠ですし、この研究を通じて言葉の力を深く考えるようになりました。
▽ロシア留学
大学3年生の後期から4年生の後期にかけて1年間、モスクワ大学の文学部に早稲田大学の交換留学で留学しました。モスクワ大学には、いろいろな国から優秀な学生が来ていて仲良くなりました。ロシア語でコミュニケーションをしますが、文化が違うので考え方が違って外国人は疲れるけど、もっと理解したいなという気持ちになりました。
私が留学したのは2006年ですが、とても生活が不便でした。夏の1か月間は、お湯が止まります。水でシャワーを浴びることになりますが、風邪をひいてしまうので、ロシア人式にお湯を炊いて水で薄めて体を拭いていました。しかも予告なしにいきなりお湯が出なくなります。モスクワの地区ごとにお湯が出なくなるということは聞いていましたが、大体いつ頃というような感じでピンポイントでは当てることができないので、ある日突然水だけということになります。
モスクワは、インフラが老朽化していて、日本と比べてとても暮らしにくいのですが、文化的資本が非常に高いです。皆さん、メトロの中でも割と純文学を読んでいます。ゲームをしている感じの人は全然いなくて、芸術や文化に対する理解度や知識が非常に豊富です。
今でもよく覚えていることがあります。私が大学で知り合った友達は、モスクワ大学に来ているような子ですからレベルが高い子ですが、経済学部で学んでいて文学は学んでいませんでした。その子と一緒にミュージカルを見に行きました。その子に「オペラとオペレッタとミュージカルの違いって何なの」と聞いたら、あきれられました。それは簡単で、オペラとオペレッタはクラシック、ミュージカルは現代音楽、オペラは歌しかないけれどもオペレッタには普通に話している部分がある。だから、ミュージカルとオペレッタは現代なのかクラシックなのかの違い、オペラとオペレッタはクラシックの部類であるけれども、オペラには話している部分がないということを教えてくれました。よく知っているなと非常にびっくりしました。そういうふうに文化的な民度がとても高いです。